 |
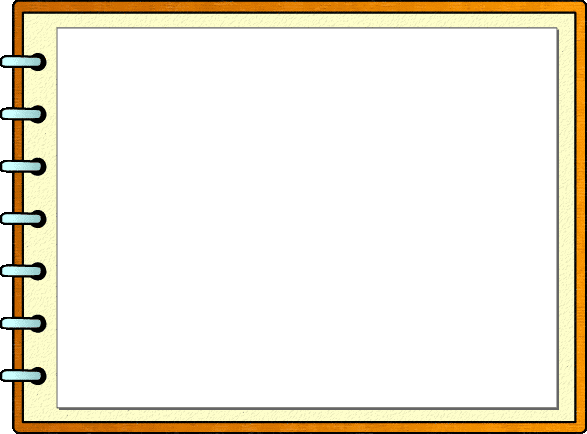 |
| ちからいし |
|
| 当時の若者が丹前に包み、袖を通し、背負って何歩、歩けるかを競争した。200キロあり、一時紛失していたが発見された。家の守り神である。 |
|
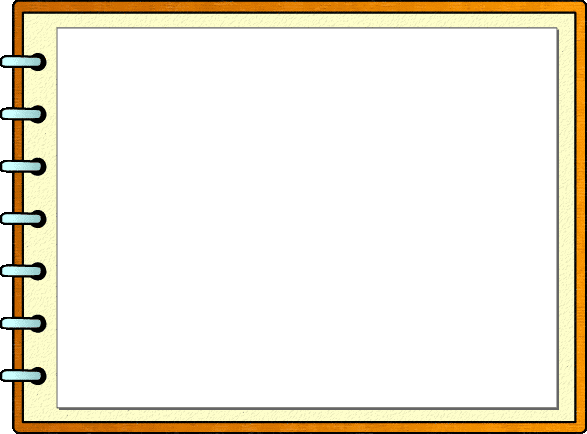 |
 |
|
ぶんぶく茶釜 |
|
明治5年頃求めたもので、5代の世帯を見てきている。 |
 |
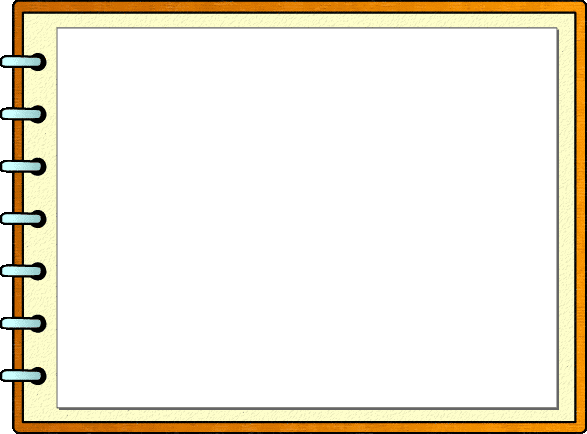 |
| たんのくるまのえべっさん |
|
| 谷(たん)の車(今の榎田地区)に水車が回り米をついていたそうな。今は道路ができ3分の1は道路より下で、子供の頃は見上げていた。この大石の下をくぐる川は5本(5橋)あり栄養が流れ込んでくるので、反当たり10俵近くの収穫が昔からあった。祭りには、その田んぼで奉納相撲がされていた。子供の頃は大石の穴に手と足を掛けて登った。 |
|
 |
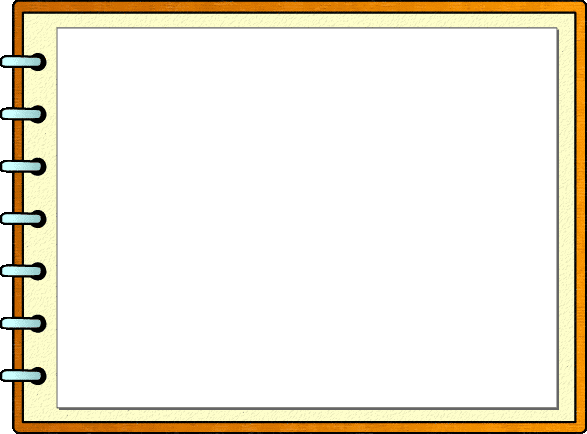 |
| 蛸壺(たこつぼ) |
|
素焼きの蛸壺を家の前浮かぶ天草四郎が談合した談合島(湯島)が見える海岸の有明の海に投げ込んでおくと付着してくる。
松葉は普通2本であるが、七福神めぐりの旅で3本を持ってきた。白い葉にの裏にささっている。 |
|
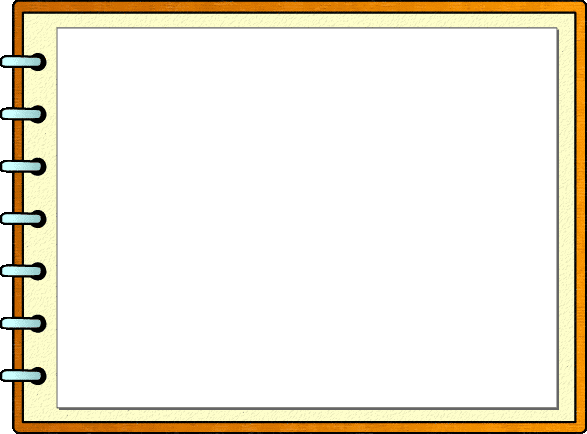 |
 |
|
有明海に浮かぶ湯島(談合島) |
|
家の庭より見える天草四郎たちが談合した島であり、古くよりここで栽培されるスイカは美味しい。魚も豊富で旬のものを食べさせてくれる。有家町の小川が一番近い。 |
 |
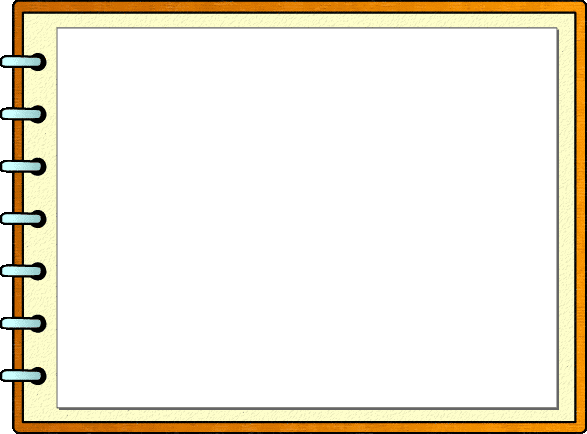 |
| 魔除けのお面 |
|
|
|
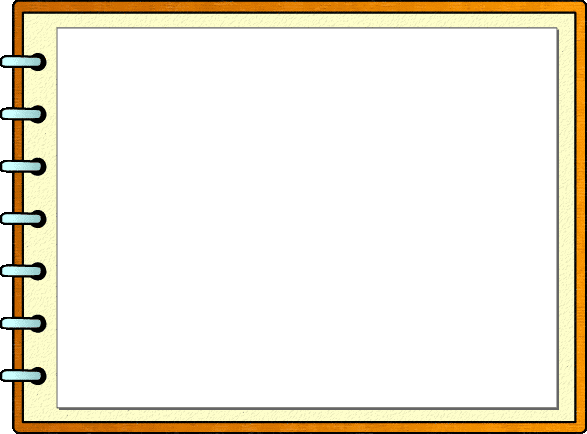 |
 |
|
エケコ人形 |
|
欲しいものを背負わせると夢がかなう人形。煙草を吸わせると喜ぶらしい。 |
 |
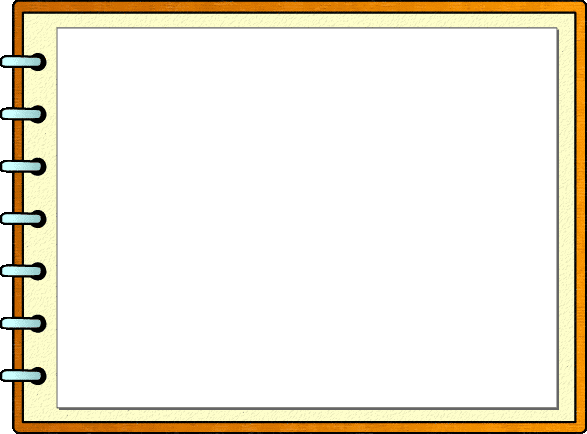 |
| インカの棍棒頭 |
|
| 空中都市マチュピチュの登り口の露店で買った。足元に無造作に置かれていたのを、指さしたらインカストーンと歯がかけた老婆は言った。 |
|
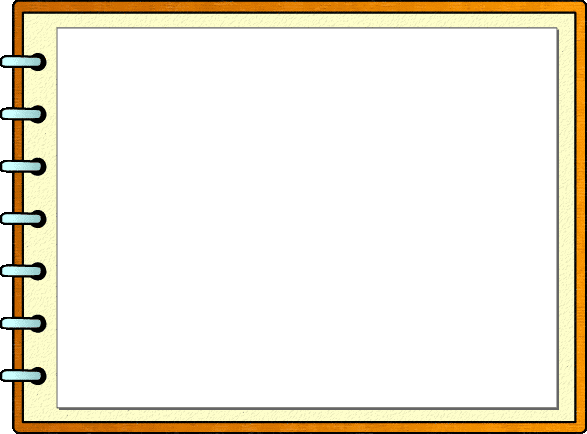 |
 |
|
世界の食材 |
|
マカ、キヌア。キャッツクロー、インカ塩、アマランサス、黒米、赤米、藻塩 |
 |
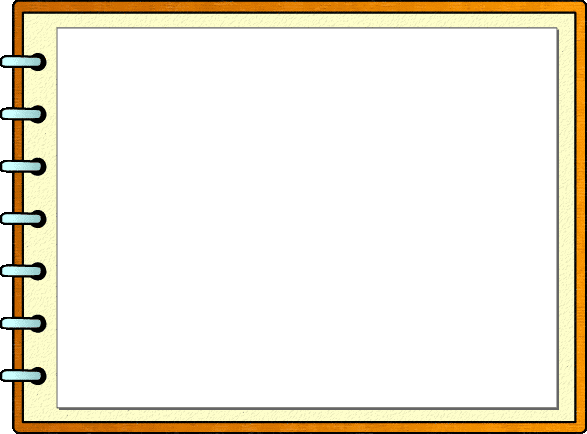 |
| 民族楽器 |
|
| ケーナ、サンポーニア、アンデス民族楽器 |
|

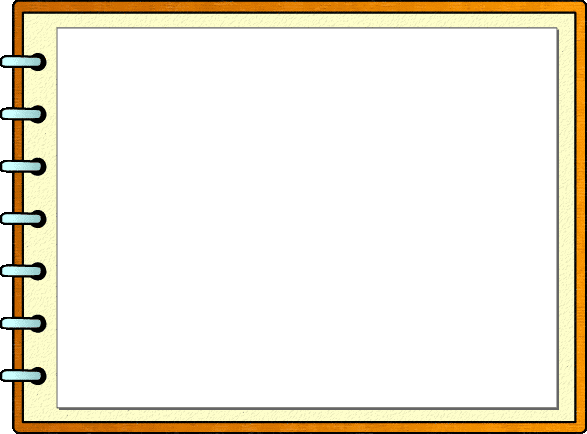
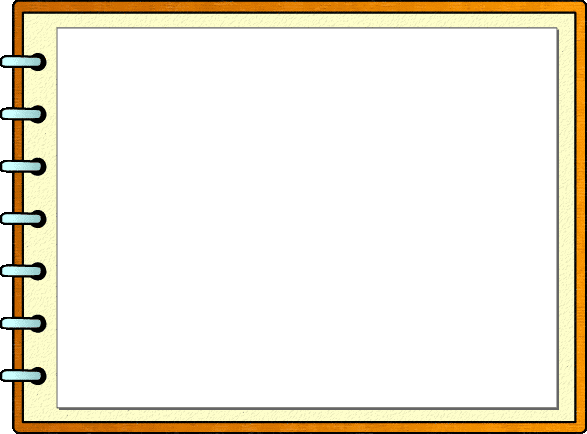


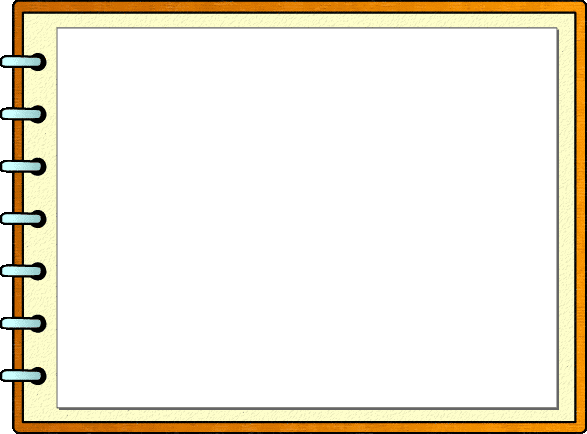

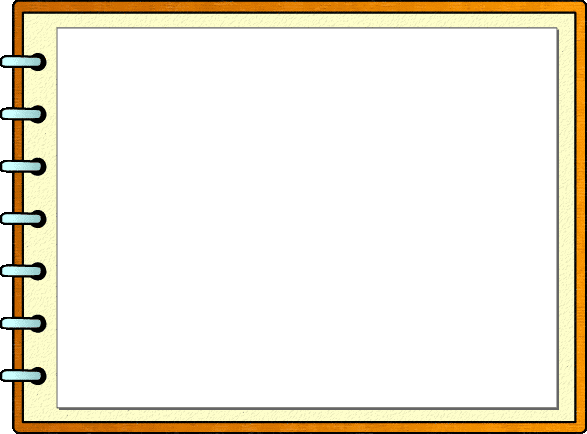
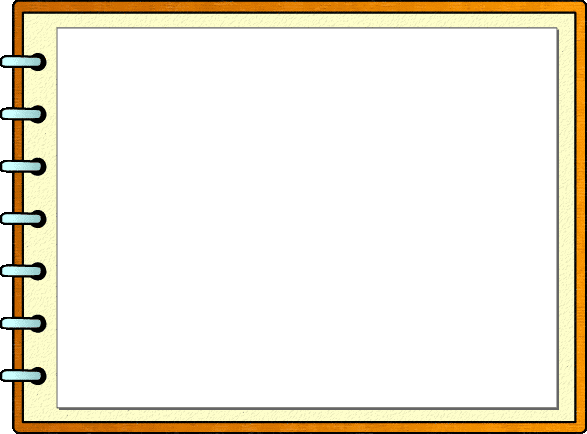


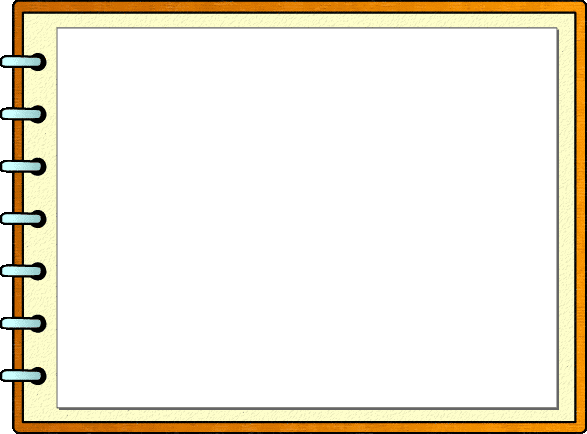
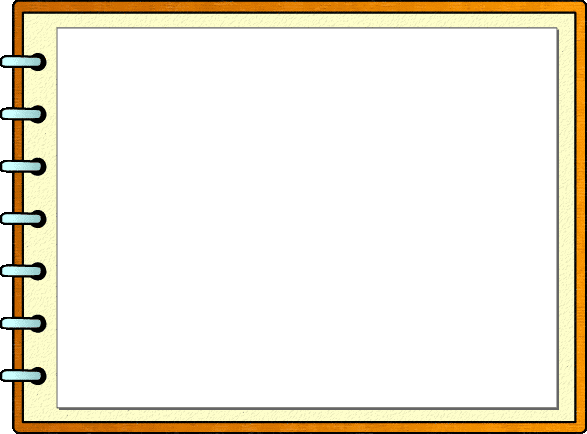


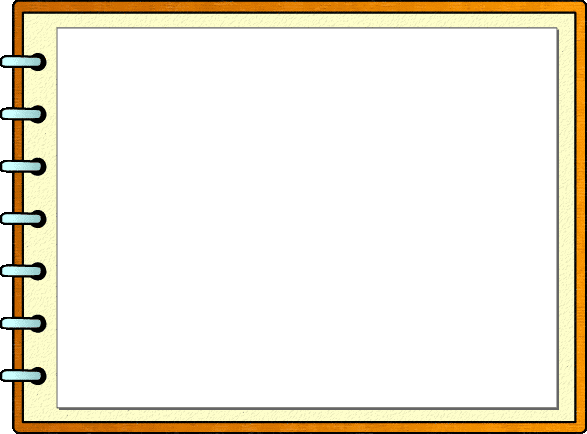
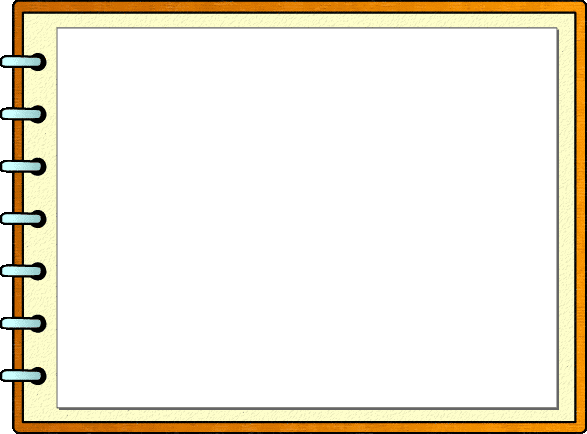


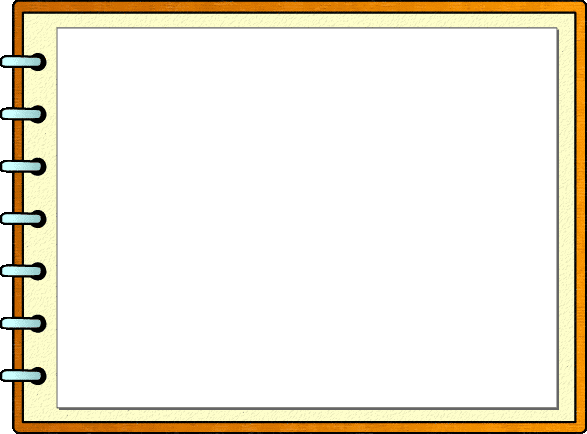
 鮎帰りの滝
鮎帰りの滝