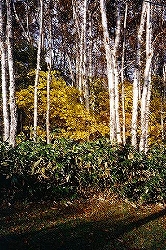人生の道草/処女詩集「もっこうの詩」
「冬じたく」
秋は自然と生き
裾野を道づれに
沈黙づたいに歩かば
紅葉も使命果たさんか
降り散る衣は冬じたく
一面敷くは風の効用
みんじりともせずは我が地の効用
あたり回らば
我が身回らんかな
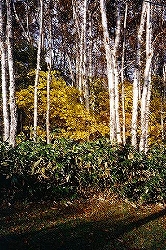
行きかうも旅人と知らしめ
過ぎし日も己と悟る
つまびらかに知り
記憶を引き下げ
沈黙づたいに歩かば
我が身回らんかな
秋は自然と生き
裾野を道づれに
沈黙づたいに歩かば
紅葉も使命果たさんか
降り散る衣は冬じたく
ぞうき か
「雑木の架け橋」
村の娘が嫁ぐとき
必ず通る小さな丸太の橋
知らずして娘らが足を止め
水に映る我が身を眺め
遊んだ遠いあの日
何時か涙がせせらぎに落ちる。

急かされて歩く足どり重く
母がこの橋を渡り終えたら
振り向くなと言った涙の声は
何時か耳を抜け山々にこだまする。
母に背負られ渡った幼い日
今度この橋をきっとあの人と渡る
彼のもとへ続く道も遠くても疲れない
何時かこの道も二人で歩く
嫁ぐ日必ず渡たり立ちすくむ
村の丸太の橋
娘は涙と一緒に流すので
水の絶えない村はずれの 雑木の架け橋
1970.4.15
民話(ふるさと昔ばなし)
「民話にひそむ音楽」
ありえ町に古くより語りつがれた民話は、
幾世代を経て今、老人の心の片隅に
わずかに残っているのにすぎません。
老人が孫に語りかけていたひととき
(縁先で日なたぼっこして話してくれたひととき)
(寝つかれない子らに話してくれたひととき)が
今の生活には必要ないかのように、子供たちの心の中に
スイッチひとつで入ってきてしまうようです。
このひとときの欠如で、語り場を失ったあなたの町や村の
財産が消え去ろうとしております。
祖先の息づかいが直に伝わる唯一のものを
子供たちの心に芽生えさせ、そして生きづかせ
貴い夢の文化財産を子供から、その子供へと
触れ伝えることができるように、今残してやりたく、
お年寄りの方を訪ねて廻っております。
何とぞ些細なことでも結構ですので、ご連絡をお待ちしております。
19927月7日 入民村ふるさと探訪局
温泉神社(四面宮)の夏越祭(なごっさん)
弘安4年7月蒙古の大軍が筑紫に押し寄せてきた時、敵中に一身三面の勇士
がが現れ、攻撃を拒み、どうすることもでき無かったとき、突如一身四面の勇士
が現れ、それを倒し、敵をなぎたおしたという。その身軽さは、あたかも飛ぶ鳥
のようであった。敵は、恐怖におののき沖に逃げてしまった。
「どこから来たのか」と尋ねると肥前国温泉山の者と答え、姿は見えなくなった。
幕府は使者を使わして捜させたが、見あたらなく、一つの社(やしろ)があるの
に気づき、尋ねると「一体四面の神様で、面ごとに名前があって、西海九国を
鎮護している」と聞き、それに違いないと幕府に報告。幕府は、大いに神の霊験
を感じ、社殿を宏荘し、祭田を寄付し報祭の礼を厚くして、神号を「四面大明神」
と改めた。そうしたことから九州各地はもちろん、以外からも参詣者は多く、武将
の尊宗する社として各地の大名は行列をなして登山したという。当時は道も悪く
険しい山道であっため、便をはかって分身末社を山麓に創建した。それが力野
の四面宮である。
温泉登山を略して肥後方面の大名は、海路大江方面に上陸し、勢揃行列を正
して有江四面宮に詣で盛大な祭典を催した。
その後、キリシタンによる神仏の破壊、島原(原城)の乱、明治以後は戦争によ
る武運長久の神として経て、いつからとなく7月29日と30日には夏一番暑い盛
りで体が弱る時期に無病息災を祈る参詣人があり、自然と露天が並ぶようにな
り、大きな賑わいであった。茅(ち)の輪をくぐり無病息災を静かに祈った。
だが、年々なごっさんがすたれていくので、昭和47年り有家町商工会青年部が
力を入れたので、昔以上のの賑わいがある。
毎年7月29日ビャーガーデン、氷水、ミスゆかた美人、花火大会、バンド演奏
夏越太鼓などのイベントや、商工会女性部によるバザー、ジュース、夏越まん
じゅうの販売、露天商60店が参道に並び実施。
3時間で18000人の人出がある。
放浪木 牧人
茅の輪
昔は茅の輪が夏越祭にはつきもので、チガヤを紙で包んで束ねたのを
輪の形に作り、神社の入り口に置いた。
この茅の輪の紙を小さくちぎって体全体を払い、その紙を懐に入れて
茅の輪を踏んでくぐれば、疫病にかからないという言い伝えがあり、
これを「夏越はらえ」と言った。
昭和60年7月29日から力野自治会の古老が寄り再現された。
又、「茅の輪」の紙を小さくちぎって体を浄めたものをサイフに入れ
ておくと、病気にかからないだけでなく、「お金もたまる」という
伝説もあると、ある古老は囁いた。
1985.7.29
たん(谷)の車のえべっさん(小川榎田)
今の榎田に水車がまわり、それで米をついていたそうな。
川を越えて登ると海を見下ろすように大石があり、その前の田んぼ
では稲刈りのあと村の若者を集めて相撲を取ってたげな。
大石にはいつの間にか恵比寿さんが乗っ取らすので恵比寿相撲と言うた。
えべっさんの横を流れ道をくぐる時5本に成っているとげな。
そいば五橋というと。
その田んぼは、守られているのか1反あたり毎年10俵とれるげな。
今もとれるげな。
力石/ちからいし(小川榎田)
かねいしのまん丸い石を昔の若者は娯楽が無かったので
丹前に包み、赤子をからうように背負い何歩。歩くか競争したと
古老はいう。何度も無くなり見つけ出しの繰返と聞く
今は、ゆったり玄関に鎮座されている。
方言をちょっくら
あるしこ(全部)
あもんじょ(化け物)
あせがれ(急げ)
いっちょか(一番いい)
いっちんち(1日)
いんにゃ(そうではない)
いっぱゃあ(いっぱい)
おめく(叫ぶ)
おずだ(目をさました)
おはやた(おはようございます)
おうけあた(ありがとう)
おうどぼうじ(腕白)
きばる(働く)
きゃなえた(疲れた) |
ぐうらしか(かわいそう)
さるく(歩く)
しかぶる(もらす)
じんべえ(よくも)
じこもん(りこう)
しょうとる(世話かける)
じゅうぐるり(周囲)
ずんだれ(だらしない)
せからしか(うるさい
そこんねけ(そこらあたり)
そこんねけ(そこらあたり)
ちゃのこ(間食)
つうえな(いらざること)
とうろし(過分に) |
とうじんなか(さみしい)
とばしる(影響)
どがんしとっと(どうしている)
ばんねんどん(終り)
はってた(行ってしまった)
ひゅむなし(無精者)
|
へぐらし(日暮らし)
べらっと(全部)
べんがべんが(赤々)
まっぽし(そのとおり)
やぜくろしか(うるさい)
よのよして(終夜)
|
「まほろば」の由来
大和は古くより国の中心で日本人は、素直に讃え、
それを誇りにしてきました。
又、我々の生まれ育ったふる里も、遠く離れても、
いつも心の誇りとしてきました。だが、私たちの国土は今、
開発の名のもと、刻一刻とふる里が破壊されつつあります。
もう一度、この日本人の心を取り戻す「心のまほろば運動」
を高田先生は説かれました。有家町から少しずつでも広げていく
運動ができないだろうかと考え1958.6.29東公民館での
ご講演終了後、直に考えをお話して、薬師寺管長高田好胤師(先生)
より直接「まほろば」使用のご了解をいただきました。
まず婦人部の会報紙を「まほろば」に改名しました。
1958.6.29(東公民館)
(現在工事中***物語続きます)