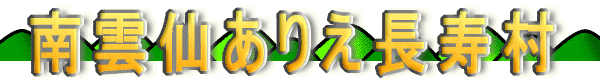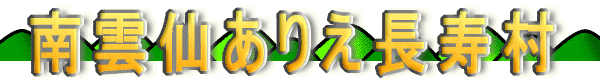 |
  村長からのご挨拶 村長からのご挨拶 
古くより国際観光地であった雲仙の麓に、長寿の里を建国しましたので、一度ご訪問ください。先人の知恵が生き、島原半島に伝わる郷土食、そして土や海や山や空からの恵みの産品をご紹介致します。
さらには、世界の長寿村に負けないように調査研究して、食材の中の食源は世界に求めて行きたいと考えています。
世界の長寿の里として、トルコのタットワン、イタリアのアルツァ−ナ村やオッローリ村、、中国の平安村や鳥恰村、ブラジルのヴェラノポリス村、日本の長野喬木村や沖縄玉城村、ケニアのマサイ族、アンドラ公国エスカルダス村、グルジアのケダ村、エクアドルのビルカバンバ、パキスタンのフンザが有名です。
最近、南米エクアドルのビルカバンバは、長寿にあやかる人達の移住等により食生活が乱れ、様変わりしており長寿村から消えています。パキスタンのフンザは、不老長寿の桃源郷とも言われいるが、治安問題で調査に難点があるためデーターが少ないが、最近は落ち着いており入国して観光できるようです。
生きるものたちが、楽しく長く生きられる食材や薬草ハーブ探しは、おのずと長寿の里にたどり着いてしまいます。長寿の里は似通っていますが、そうでない村は、幾通りの不幸なものが存します。
食材には2通りのものがあり、いわゆる命を支える食材(食源)と命を育む食材(食育)とがある。風土によって育んだものとの調和によって、楽しく長く生きられる美味しい食材があると思います。いわゆる主食とそれに付随して食する食材は、おのずと違いがあり先人の智恵が歴史を重ねるながら組み込まれていることと思います。
標題の「水酵酸(スイコサン)長寿食」の「水」は、生まれ育った地域の土や海や空や水などから生じる産品を季節に合わせて食べることが生きていく上で重要に成っています。科学的に分析証明され、身体に良き成分の食材は数多くありますが、それらだけを食べていても、身体が受け付けないと何にもなりません。
続いて「酵(コ)」は、発酵食品で人類の歴史の中で必然的に生まれ、同時にそれを育んできた先人の知恵の結晶で、未来に残すべき最高の食品であります。東京農大の小泉教授によれば「食材の発酵の前と後を比較してみると発酵菌という微生物が介在するだけで、かくも旨味が増大するものか」と発せられます。
現在は原価圧縮、長期販売するための添加物、保存料、化学調味料を混入した食材が溢れ、現代人の体を少しずつ蝕んできています。命を支えるはぐくむ大切な食を真剣に考えていく必要があります。
次に「酸(サン)」は、発酵食品の中で胃腸を元気にする酸であり、体の酸化を押さえる酸であり、コーカサス地方のケフィア、カスピ海ヨーグルト、マツオーニや蒙古のクーミス、インドのダーヒなどがあります。又、ブルガリアやトルコをはじめ黒海とカスピ海にはさまれたコーカサス地方は長寿の国として有名で、グルジア共和国は、2000年の前から代々受け継がれたきたマツオーニ(発酵乳)を食べてきた。母乳に恵まれない乳児に与えていたもので、免疫の向上及び感染予防効果もあると考えられています。
最後に成りましたが、長生きしたいなら、日本の女性の心や体に近づくことと、女性の身体の仕組を考えた食生活をすることです。
さらには、両親やその兄弟、近年の家系の特徴(病気等)を研究して、それらに打ち勝つ生活をして行くことです。 |
 郷土の長寿食 郷土の長寿食 |
◆幻の浮き島
|
 |
年に何度が現れ、浅瀬を渡って上陸します。マテ貝の宝庫です。3年くらい前までは、積み重なった石に「つがね」がたくさん下ってきており、バケツに一杯の人もいました。今は砂に埋もれています。右手には、満潮から干潮に至るとき魚を封じ込める、石を積み重ね何百メートルも続く「スキ」の跡があります。中須川の方の石原(いしばら)には、穴たこ、あさり、ほうじょさん、なまこ、ねこぎゃ(お手玉)、ひょひょろが季節に合わせて取れます。満ち潮の時、潮先ガンバが波打ち際で踊ります。写真は小川の浜より中須川の浜を望む(5月4日撮影) |
| ◆マテ貝 |
 |
干満の差が大きい有明海。浮き島の砂原を少し掘ると穴がたくさん出てくる。その穴に塩を入れてやると、塩が満ちてきたと、マテ君が勘違いして飛び出して来るのを、つかんで引っ張り上げる。ゆっくいと引っ張らないと「ドンベン」が切れてしまいます。丁度、ロケットの噴射や蝋燭の炎に似ています。一番旨いところである。一度に塩を入れて行くと、忙しくて、ゲームセンターのモグラ打ちの状態で、他から来た人を連れて行くと、子供より大人がはまって感激してしまいます。 |
| ◆ほうじょさん◆みいなみそ |
 |
塩茹でしてペンチで、下の方から4分の1位の所を切り、上の方から吸うと、口の中に勢いよく磯の香りをが飛び込んでくる。コリコリして美味しくて酒のつまみにもってこい。 |
| ◆小川の浜より湯島(談合島) |
 |
天然わかめ草(ネカブはとろろ)→みる草・とさか草→ところてん草→英国草(いぎりす草)と季節は移り変わります。3月浜は救護石(きゅうごいし)までひっころがすと古老は言われ、魚の宝庫だったそうです。船はこれを目安に横着けして、飛び移り、飛び石づたいに行けば、浜んこらより有家を縦断する道路があります。その道は「たんのくるまのえべっさん」の横を通ります。小川の浜より湯島を望んでいます。手前に見えるのは、ワカメが刈り取られた後の茎が見えます。救護石が少し見える頃に船で取るようです。 |
| ◆トコロテン草(天然) |
 |
◆石の上にトコロテン草と右に石に根ざした半分
海水に浸かったワカメが見える。 |
◆海草の宝庫
|
 |
◆ネカブをたたいて、トロロ作り。酢と醤油を入れて
あったかいご飯に掛けて食べる。
|
| ◆せっか(牡蠣)天然 |
 |
◆石に張り付いた小粒牡蠣(カキ) |
| ◆ナマコ ◆赤ミル |
 |
◆左がナマコ(赤)
◆良く水洗いして、熱湯で1秒、酢醤油で食する。
天然もので、すこぶる身体に良い。
|
| ◆穴タコ |
 |
◆石をひっくり返したら、穴たこが出てきた。 |
| ◆即席カップ有家そうめん層めん |
 |
◆ハイブリッド輪状二層めん
◆手あぶりグルメそうめん
◆地獄そうめん
◆ふしそうめん |
| ◆即席有家そうめん |
 |
◆袋タイプ |
 母なる食材 母なる食材 |
 |
◆スーパーキヌア |
 郷土の長寿食 郷土の長寿食 |
 英国(イギリス) 英国(イギリス)
|

英国(イギリス)
朝早く起きて、朝市で買ってきました。ふるさとの味がするおばちゃんの手作り品です。

(浜んこら市)
思い思いの手作りの商品を持ち寄る、アンデスペルーのピッサク市場をふと思い出しました。

英国(いぎりす)
ありえ町の小川(こがわ)海岸(有明海)に生息する海草。地元では「いぎす」と呼ばれ、学名は紅藻イバラノリ属の「カズノイバラ」である。 |
■島原南部の有明海に面した地域で、6月の大潮の時、潮が引いた沖に出て、「いぎす」という海草を採取します。足から腰ぐらいまで水につかり、綿帽子のようにふわっと浮かんでいる濃いえんじ色のいぎすを、金属製の八つ手のような「ごうかき」という道具でひっかけます。石についている根は簡単にはずれ、細かく枝分かれした固まりがとれます。てんぐさより長く、さわるとしゃりしゃりして心地よいのがこの海草の特徴といえます。
島原の乱後、この地に移住してきた四国の人たちの影響で、今治(愛媛県)あたりのいぎす豆腐がもとであるといわれています。干しいぎすをさらすと、もとの一斤が約40匁に減ります。うるち米の新しい米ぬか5合を布袋に入れて水2升の中でもみ出し、一番ぬか汁でいぎす40匁を浸して洗います。水気をしぼって、二番ぬか汁2升くらいを入れ、火にかけて練る。ぬか汁は少しとりのけておき、加減を見ながら加えていきます。いぎすは水やもち米のぬか汁ではよく溶けませんが、うるちぬか汁で30分ほど煮ると、不思議と溶けてきます。
中に入れる具は、にんじん、きくらげ、しいたけ、魚(さば、いわし、白身の魚など)を小さく切って砂糖醤油で煮ておきます。落花生は炒って渋皮をとり、ふきんに包んでたたいておきます。豆腐は小さくさいの目切りがよいです。
いぎすがよく溶けてとろみが出てきたら、具と煮汁を入れて味を整え、また10分くらい練って、ねぎの小口切りを散らした流し箱に流して固めます。
ようかんのように切って大皿に盛って出すが、中の具のおいしさと、のどの通りのよさで、ほかにごちそうがあっても、つい手が出てしまう素朴な郷土料理です。
また、中に具を入れないものを白いぎりすといって、仏事に用います。細く切って、ごま醤油や白あえで食べます。この本いぎすに対して、もう一つ藻いぎす(えごのり)というものがあります。これは藻につく赤い花で、藻をとってきて花を集めます。この花を、ぬかではなく味噌を水に溶いた汁で炊くと、こりこりしておいしいいぎりすができます。
■由来
島原は、まちの中央に眉山がそびえ、前面には不知火で名高い有明海に抱かれ、山海の珍味が豊富で、しかも手軽に食膳に供されます。この具雑煮は寛永14年(1637年)の島原の乱の時、一揆軍の総大将であった天草四郎が、約37000人の信徒たちと籠城した際、農民たちに餅を兵糧として蓄えさせ、山や海からいろいろな材料を集めて雑煮を炊き、栄養をとりながら約3ヶ月も戦ったといわれています。材料は、山芋、ゴボウ、レンコン、白菜、椎茸、鶏肉、蒲鉾、焼きあなご、卵焼き、春菊、もち等10数種類の具がふんだんに使われています。 |
|
| ■ 六兵衛 |
 |
■由来
今から約200年前(1792年)島原市の背後にある眉山が崩落し、有明海には津波が巻き起こり、沿岸一体に大被害を与えたのが島原大変です。その後、島原半島は食糧危機に見舞われ、さつまいもを主食とするようになりました。
その当時、深江村の農家の六兵衛という人がさつまいもを粉末にして山芋を入れ、熱湯でこねて、うどん状にしたものを作ったのが六兵衛の始まりといわれています。
だし汁は自家製の醤油を用い、ねぎの薬味だけを添えて食したといわれます。素朴な食べ物で、郷愁を誘う郷土料理です。 |
|
| ■ ガンバ |

◆しまばら温泉観光協会の
ご好意より掲載しています。
|
■由来
島原ではフグのことを「がんば」と呼びます。江戸時代、フグが猛毒をもつため、藩主がフグ食の禁令を出していましたが、それでも危険をかえりみずおいしいフグを食べる人が後を絶たなかった多かったようです。
そうしたことから、棺(ガン)ば(を)そばに用意してでも食べたいという意味で「がんば」と呼ぶようになったともいわれています。有明海には冬、五島灘やその周辺にいたトラフグが3月から5月にかけて産卵にやってきます。島原湾は春がフグ漁の最盛期で、そのトラフグを使ったものが「ガンバ料理」です。とても美味しいため、養殖トラフグや有明海産ナシフグも登場するようになってきました。
■料理
郷土料理の一つに「がねだき」があります。まず、「がんば」をぶつ切りし、火にかけ、から炒りをして、水気を切ります。醤油、酒またはみりんで味をつけ、(砂糖は使用しない)梅干しとニンニクの葉を加え煮汁がなくなるまで煮込みます。
風味、かおりとも絶品といえ、島原独特のものです。他にがんばの身を多少厚めにそぎ切りにして薄塩をしたあと、熱湯にさっとくぐらせ冷水にとり、梅干しの身を醤油、酒、酢で作ったタレともみじおろしなどの薬味と一緒にいただく「湯引き」も珍味として食されています。 |
|
| ■ 手延べそうめん |
 |
■
由来
雲仙岳の裾野がなだらかに広がる島原地方は寛永14年(1637年)の島原の乱で、すっかり荒れ果てましたが、その後、農村復興のため小豆島から移住した移民の人々の中にいた手延べそうめん造りの名人が藩主の保護をうけ、その技法を島原地方にもたらしたという説、また、中国から渡ってきた後、島原地方の風土に合い根付いたとの説があります。
島原地方の豊かな農地に育まれた良質の小麦粉と、名水百選の一つに選定された湧水、おだやかな気候風土に恵まれ、独特のコシと風味のあるそうめんが作られています。
■
ゆで方のこつ
まず、多めのお湯(そうめん五束=250gに対して水約2.5l=約1升4合の割合)を充分沸騰させます。沸いたら、そうめんの束を解きよくほぐして入れ、再び沸き上がったときカップ半分ぐらい差し水をします。2回それを繰り返せばゆであがりです。そうめんはざるにあげ、冷水の中でかきまぜ油抜きします。再び容器に取り、冷水に浮かし、味汁に配してお召しあがりください。 |
|
| ■ ざぼん漬け |
 |
ざぼんとは、ポルトガル語の「ザンボア」から転じた言葉といわれています。材料はざぼんの皮、砂糖、水アメ、蜂蜜等を使用して作られます。 |
|
| ■ 寒ざらし |
 |
白玉粉で作った小さな団子を「島原の湧水」で冷やし、蜂蜜、砂糖等で作った特製の蜜をかけたもので、口の中でとろけそうな上品な甘さと喉越しのよさが人気の素朴な郷土の味です。
中国にも寒ざらしに似たものがあり、「元子」(ユアンツ)といいます。また、団子の中にいろんな種類の具が入っているものがあり、これは「湯団」(ユーディアン)と呼ばれています。寧波(ニンポー)、温州で食べられているといいます。 |
|
| ■ 具雑煮 |
 |
■料理
島原の雑煮というのは、昔は大なべに近辺で取れる野菜や魚などを大量に入れて煮込むのが特徴でした。また、だしの取り方は各家庭で違いますが、カツオだし、いりこ、かしわ、あご、こんぶなどがよく使われています。
料理自体はきわめて単純なものですが、このだし汁にごぼう、しいたけ、かしわ(鶏肉)、焼アナゴなどの10数種類の具の煮汁がうまく調和し、うまみを出していきます。この他に、長崎白菜といわれる白菜とは異なるチンゲンサイによく似た野菜も使用する場合もあります。 |
|